つらい気持ちを抱えている方へ
つらいこと、苦しいこと話してみませんか。その気持ちを誰かに伝えるだけできっと楽になります。

あなたの心を覆っている悩みはどんなことでしょうか。
職場の人間関係に悩んで、出勤するのがつらく感じる。
ハラスメントや圧力的な態度により、心身に不調を感じている。
職場でいじめにあっているが誰も助けてくれない。
解雇、派遣切れにあって経済的に困り、家賃も払えず、困り果てている。
病気になって働くことができず、生活が成り立たない。
悩みが昂じてうつ病になってしまい、死にたくなった。
家族に迷惑をかけ、申し訳ない。そんな自分は生きている価値がないと思い込んでいる。
そのつらい思いを言葉にし、暗いトンネルを抜け出しましょう。
あなたの力になる場所が、人が必ず傍にいます。
あなたは一人ではありません。
ストレストこころ
「ストレスなんていらない、もうごめんだ」・・・そう思うこともあるかもしれません。
けれど、私たちはストレスのない世界では生きていけません。
大切なのは、“なくす”のではなく、“うまくつきあう”こと。

まずは、ストレスがたまったときのサインを知ることで、こころの病気の予防にもなります。周囲の同僚や部下、家族の変化に気づく力にもつながります。
ストレスをうまくコントロールする方法を知ることも大切です。
こころが疲れたときや、つらいとき、困ったときのために、セルフケアの方法を知ることで、つらい気持ちも軽くできるでしょう。
また、強いストレスを受け続けることで、私たちは「こころの病気」になることもあります。ここでは、こころの病気の種類や症状、治療法についてもご紹介しています。
ストレストうまくつきあう

ストレスとは、私たちが仕事や日々の生活で感じるプレッシャーのことです。
成果を出そうと真摯に取り組むからこそ、この感情は生まれます。
重要なプレゼンテーションやプロジェクト前など、適度なストレスは集中力や意欲を高め、最高のパフォーマンス発揮に繋がる側面もあります。
しかし、そのストレスが過大であったり、長期にわたって続いたりすると、 心身の健康を著しく損なう原因となります。
ストレスとうまく向き合うことは、様々な疾病の予防になるだけでなく、充実したキャリア形成、ひいては豊かな人生を送る上でも不可欠です。
ここでは、ストレスと上手に付き合うための具体的な方法を知り、実践していきましょう。
ストレスって何?
たとえば、あなたがプレゼン準備などで、大勢の前で発表しなければいけなくなった、という状況を思い浮かべてみてください。「うまくやれるだろうか」という緊張から、心臓がドキドキたり、手に汗をかいたり、しませんか。
これは、ストレスに対抗するために、いわば体が頑張っているわけです。

「うまくできなくてもよい」と思うとあまり緊張しませんね。ですから、緊張したりドキドキするのは悪いわけではありません。それだけ頑張る気持ちが強いということです。
しかし、強いストレスがかかった状態が続くと、やがて、こころと体は疲れてしまい、「もう頑張れない状態」になってしまいます。これらは、みんな自然な反応です。
ところが、ここでさらに頑張りすぎてしまうと、私たちのこころと体は、いよいよ調子をくずしてしまうでしょう。
ストレスを感じやすい状況
もし今、「なんとなく調子が悪い」「いつもより疲れが取れない」と感じているなら、もしかするとそれはストレスによるものかもしれません。知らず知らずのうちに、頑張りすぎているのかもしれません。
私たちがストレスを感じやすい場面には、次のようなものがあります。

思い当たることはありませんか?
・重要なプレゼンや、人前での発表を控えている
・異動や職場の人間関係の変化で、生活環境が大きく変わった
・家族の体調不良や介護など、家庭内の事情に気を取られている
ストレスの受け方は人それぞれです。強く感じる人もいれば、あまり気にならない人もいます。ですが、たとえ一つひとつの出来事は小さくても、それらがいくつも重なると、心身に大きな負担となることがあります。
たとえば、業務の繁忙期に加えて家庭の事情が重なったり、新しい環境に慣れないうちに別の課題が発生したりすると、誰でも大きな負担を感じます。
そんなときは、できるだけ自分の負担を軽くする工夫が必要です。
ストレスのサイン
ストレスを感じた際、皆様はどのような状態になり、どのような対処を取られますか? 私たちは、自身のストレスに無自覚なまま、過度な負担を重ねてしまうことが少なくありません。結果として、気づいた時には心身ともに疲弊していることもあります。このような事態を避けるためにも、まずはストレスの「兆候(サイン)」に早期に気づくことが重要です。

特に、業務で何かに集中し、没頭している時ほど、ストレスの自覚が遅れる傾向にあります。
そこで、自身のストレスサインを正確に把握しておくことが極めて重要になります。
自身のストレスサインに早期に気づき、適切に対処できるようになることで、心身の健康を維持し、業務パフォーマンスの向上にも繋がります。
日頃から自身のストレスサインに意識を向け、適切なセルフケアを心がけましょう。
早期の気づきと適切な対処は、皆様の心身の健康、ひいてはキャリア形成において不可欠です。
こころのサイン
- 不安や緊張が高まって、イライラしたり怒りっぽくなる
- ちょっとしたことで驚いたり、急に泣き出したりする
- 気分が落ち込んで、やる気がなくなる
- 人づきあいが面倒になって避けるようになる
体のサイン
- 肩こりや頭痛、腹痛、腰痛などの痛みが出てくる
- 寝つきが悪くなったり、夜中や朝方に目が覚める
- 食欲がなくなって食べられなくなったり、逆に食べすぎてしまう
- 下痢したり、便秘しやすくなる
- めまいや耳鳴りがする
ストレスは早めの対処が大切
ストレスの兆候に気づいた際は、できる限り早期に、一人で抱え込まず、積極的に周囲に相談し、適切な支援を求めるようにしましょう。
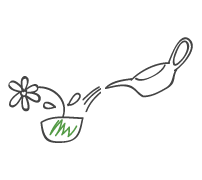
セルフケアは、ご自身のストレスを管理するための効果的な手段です。例えば、信頼できる人に話を聞いてもらったり、趣味に没頭したり、質の高い休息を取ったりすることで、精神的な負担が軽減されることは少なくありません。今抱えているストレスは、ご自身でコントロールできる範囲にあるか、客観的に評価することが重要です。
もし、数日経っても不調が改善しない、精神的な不安定さが続く、あるいは意欲の低下や疲労感が慢性化している場合は、過大なストレスが心身に深刻な影響を及ぼしている可能性があります。
そのような状況に陥った際は、迷わず、心身の専門家(産業医、カウンセラー、医療機関など)に早期に相談し、専門的な助言を得ることを強くお勧めいたします。
こころのSOSサインに気づく
私たちは皆、日々の生活を充実させ、前向きな気持ちで過ごしたいと願っています。しかし、現実には常に理想通りとは限りません。人間関係の課題や業務上のプレッシャーなど、様々な要因によってストレスを感じることは避けられない現実です。
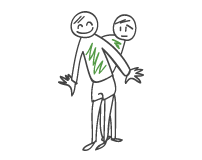
こうしたストレスによって、一時的に気分が落ち込んだり、意欲が減退したり、 あるいは苛立ちを感じやすくなったりすることは、人間として自然な反応です。
しかしながら、このような精神的な不調が慢性化し、解消されないまま心に留まり続けると、結果として身体的な不調に繋がる可能性もあります。
そのような状況が続く場合は、精神的な「疾病(疾患)」の初期症状である可能性も視野に入れるべきです。
また、精神的な不調が身体症状として現れることもあります。病院で検査を受けても明確な原因が見つからない場合、その背景にストレスが潜んでいる可能性も考慮すべきでしょう。心身の不調に気づき、それが長期にわたって続く場合は、ご自身の「心」が助けを求めているサイン(SOS)と捉え、適切な対応を取ることが重要です。
気分が落ち込む
業務での成果達成は大きな喜びですが、期待に反する結果や困難な状況では、落胆やストレスを感じることは自然です。
しかし、日々の疲労が取れない、睡眠や食欲の不調、人との交流を避けるといった状態が長期にわたる場合、それは「うつ病」の兆候かもしれません。
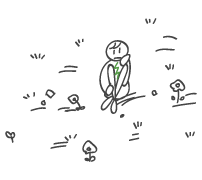
症状が進行すると、これまで行っていた業務や活動への意欲が著しく低下することがあります。
うつ病の初期には、精神的エネルギーの枯渇を感じ、集中力や判断力の低下、無力感に苛まれることがあります。「なんとなく調子が悪い」といった状態から、心身の不調が顕著になり、日常生活に支障をきたすような変化に気づいた際は、早期の対応が不可欠です。
決して一人で抱え込まず、社内の産業医、人事部門、あるいは外部のカウンセラーなど、専門機関へ速やかにご相談してください。
不安でたまらない
過度の緊張や不安は、業務効率の低下や人間関係の悪化を招くことがあります。しかし、そうした不調が長期化し、業務遂行に支障をきたす、あるいは日常生活にまで影響が及ぶ場合は、「不安障害」の可能性も考慮する必要があります。
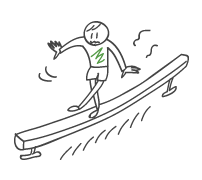
不安障害は、特定の状況やストレス要因によって引き起こされるケースが多いですが、その兆候は多岐にわたります。例えば、動悸や息苦しさ、発汗、めまい、胸部の圧迫感、あるいは些細なことで過剰に反応するといった身体症状に加え、常に神経が張り詰めた状態、落ち着かない感覚、漠然とした不安感に襲われるといった精神的なサインも現れることがあります。
特に強い不安発作が繰り返し起こる場合は、「パニック発作」の可能性も考えられます。このような症状に気づいた際は、決して一人で抱え込まず、心療内科や精神科などの専門医に早期に相談し、適切な診断と治療を受けることをお勧めいたします。早期の受診が、回復への第一歩となります。
こころと体のセルフケア
多忙な業務や人間関係の中で、私たちはストレスを感じがちです。会議、納期、予期せぬトラブルなど、プレッシャーを感じる場面は多々あるでしょう。

十分な休息が取れず疲弊したり、些細なことでイライラしたり、あるいは気分が落ち込んで集中力が続かないといった経験はありませんか。
これらは、ご自身の心身からの「危険信号(アラート)」と捉えるべきサインです。
セルフケアはもちろん重要ですが、心身の不調を感じた際は「早期の対応」が何よりも大切です。早めに対処することで、回復も早まり、より深刻な状態への進行を防ぐことができます。
自身の心身のサインに気づき、適切なセルフケアと早期の対処を心がけ、健やかな心身で日々を過ごしましょう。
疲れたとき、つらいときに自分でできることは?
理由もなくイライラしたり、心身が疲弊していると感じた際は、思い切って「心と体のセルフケア」を試してみることをお勧めします。下のページに紹介する6つのメニューから、ご自身に合ったものを選び、実践してみてください。
ただし、不眠で身体がつらい時や、食欲不振で食事が十分に摂れていない時などは、無理に運動メニューをこなそうとせず、休息を優先してください。
つらい時は一人で抱え込まず、信頼できる同僚や上司、家族、友人に悩みを打ち明けることも、立派なストレス解消法です。その日の気分や体調に合わせて、無理のない範囲でメニューを選び、実践していきましょう。
体を動かす
身体を動かすことは、心身の健康を維持し、ストレスを効果的に軽減するための重要な手段です。

ウォーキングや軽いジョギング、ストレッチ、ヨガなど、ご自身のライフスタイルや体力に合わせた運動を取り入れることで、気分転換が図れます。適度な運動は、自律神経のバランスを整え、睡眠の質を高め、集中力の向上にも繋がります。また、気分転換になるだけでなく、達成感を得ることで自己肯定感が高まり、ストレスへの耐性も向上させることが期待できます。
多忙な日々の中でも、意識的に体を動かす時間を作り、心身のリフレッシュを図りましょう。短時間でも継続することが大切です。
今の気持ちを書いてみる
心の中に抱えている感情や考えを言葉にすることは、ストレスを軽減し、自己理解を深める有効な手段です。頭の中で漠然と考えているだけでは整理がつかない感情も、書き出すことで客観視でき、問題解決の糸口が見つかることがあります。
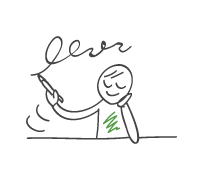
日記やジャーナリングのように、定期的に感情や思考を書き留める習慣を持つことで、自身の心の状態をより深く認識できるようになります。過去の経験や、その時に抱いた感情、思考を記録することで、自己成長の過程を振り返り、将来の行動計画を立てる上での洞察を得ることも可能です。
これは、誰かに見せるためではなく、完全に自分自身のための行為です。心の整理だけでなく、客観的な視点を得ることで、冷静な自己分析に繋がり、建設的な対応へと導くことができます。
どのような形式でも構いません。日付と共に、その日の出来事や感じたこと、考えたことなどを自由に書き出してみましょう。
腹式呼吸をくりかえす
不安や緊張が高まると、呼吸が浅く速くなりがちです。これは、無意識のうちに体が「非常事態」モードになっているサインかもしれません。
心身が疲弊している、あるいはストレスを感じている時は、意識的に「深い呼吸」、特に「腹式呼吸」を試みてください。

■ 腹式呼吸の具体的な実践方法
座っていても立っていても構いません。リラックスした姿勢で、まずお腹に手を当ててみましょう。
基本的な腹式呼吸は、息を吐き出すことから始めます。約3秒かけて口からゆっくりと息を全て吐き出し、その後、自然に鼻から息を深く吸い込みます。この一連の呼吸を5~10分程度繰り返してみましょう。
■ 心身のリラックスを深める「弛緩呼吸」
さらに、息を吐き切った後、もうこれ以上吸い込めないと感じるほど深く呼吸をすると、より深いリラックス効果が得られます。これを「弛緩呼吸」と呼びます。
■ 呼吸への意識集中で心を整える
呼吸中に余計な思考が浮かんだとしても、無理に打ち消そうとせず、その思考を受け流し、再び呼吸に意識を戻しましょう。
腹式呼吸は、心身のバランスを整え、ストレスを軽減する上で非常に効果的なセルフケアです。日々の生活に積極的に取り入れ、心身の健康維持にお役立てください。
「なりたい自分」に目を向ける
困難な状況やストレスに直面した時、私たちはつい「つらい状況」や「できないこと」に意識が向きがちです。しかし、そんな時こそ、自身の「なりたい姿」や「理想の未来」に目を向けることが重要です。具体的なイメージを持つことで、現状への対処だけでなく、未来への活力を生み出すことができます。
そのためには、まずご自身の「なりたい姿」を具体的に描いてみましょう。
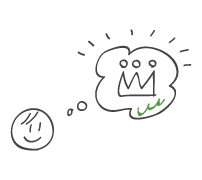
そして、その「なりたい自分」になるために、現状と目標のギャップを認識し、どのような課題を克服する必要があるかを具体的に考えてみてください。その過程で、周囲の人々がどのように変化し、自分自身がどう成長していくか、より具体的なイメージが湧いてくるでしょう。小さなことでも良いので、今日からできることを目標として、実践を重ねることが大切です。
例えば、「人間的に成長し、周囲から信頼される自分になりたい」と考えるなら、まず「早朝出勤で落ち着いて業務に集中する」「周囲に積極的に声かけをする」といった、具体的な行動から始めてみましょう。
このように、具体的な行動目標をクリアしていくことで、自己肯定感が高まり、自信を持って業務に取り組むことができます。
漠然と考えるだけでなく、具体的な行動を積み重ねることで、自身の未来を切り拓くことができるでしょう。
音楽を聞いたり、歌を歌う
「音楽」は、私たち自身の心と体に深く響きかけ、感情を揺さぶる力を持っています。
アップテンポの音楽は、エネルギーを与え、閉塞感を打ち破るきっかけとなることがあります。歌詞に共感したり、心に響くメロディに出会ったりすることで、言葉にできなかった感情を表現し、心が解放される経験は少なくありません。
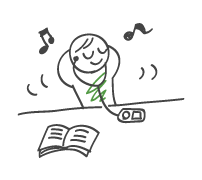
また、好きな音楽に合わせて体を動かしたり、歌を歌うことも、気分転換に非常に効果的です。例えば、自宅でゲームやリモートワークの合間に、ただ聞くだけでなく、一緒に歌ったり、手拍子を打ったりするだけでも良いでしょう。
気分が優れない時でも、音楽を「聞く」だけでなく「体を使って表現する」 ことで、心の奥底に溜まった感情を発散できます。不安やイライラが解消され、気分がきっと晴れやかになるはずです。
このように、音楽や歌を通じて感情を表現することは、手軽で効果的なセルフケアです。ぜひ、日々の生活に取り入れてみてください。
失敗したら笑ってみる
私たちは、どんなに注意を払っていても、時に失敗や思い通りにいかない状況に直面することがあります。そんな時、つい自分を責めたり、落ち込んだりしがちです。
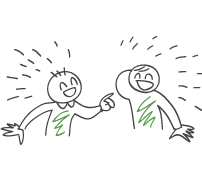
しかし、困難な状況や失敗に直面した時こそ、ものの見方を変え、それを「笑い」に変えることで、心がぐっと軽くなることがあります。
もし信頼できる仲間がいて、失敗について正直に話せるのであれば、一人で抱え込まずに「やっちゃったな、自分!」と笑い飛ばしてみましょう。
「そんなことありえない」「馬鹿げている」と感じるかもしれませんが、これはユーモアのセンスや自己肯定感を高める訓練でもあります。無理に笑う必要はありませんが、少しずつ、自分以外の誰かの失敗に寛容になるように、広い視野で物事を捉える練習にも繋がります。
そして、時には「笑い」を周囲の人と共有することで、リラックスでき、心の負担を軽減できるはずです。失敗をネガティブに捉えるだけでなく、前向きな学びの機会に変える柔軟な姿勢を育んでいきましょう。
ストレスが続くと「こころ」にどんな影響がある?
ストレスが長引くと、気分が落ち込んだり、やる気が出なくなったりと、心の不調につながることがあります。
通常の落ち込みと「うつ病」の違いは、その状態が2週間以上続くかどうかがひとつの目安です。
うつ病とは
うつ病は、脳内の神経伝達物質「セロトニン」「ノルアドレナリン」が減ってしまう病気だと考えられています。これらの神経伝達物質は精神を安定させたり、やる気を起こさせたりするものなので、減少すると無気力で憂うつな状態になってしまいます。
ですから、うつ病は決して怠けているわけでも、気の持ちようで何とかなるものでもありません。しかも、うつ病は日本人の約15人に1人が一生のうちにかかるという非常にありふれた病気です。早めに適切な治療を受けることが必要です。
こんな症状が続いていませんか?
次のうち5つ以上(1か2を含む)が2週間以上続いていたら、専門家に相談することをお勧めします。
- 悲しく憂うつな気分が一日中続く
- これまで好きだったことに興味がわかない、何をしても楽しくない
- イライラする、怒りっぽくなる
- 自分に価値がないように思える
- イライラする、怒りっぽくなる
- 集中力がなくなる、物事が決断できない
- 「死にたい」「消えてしまいたい」「いなければよかった」と思う
- 食欲が減る、あるいは増す
- 眠れない、あるいは寝すぎる
- 疲れやすく、何もやる気になれない(体がだるい、生気がない)
- 肩こり、頭痛、めまい、吐き気などの身体症状が出る
- 下痢や便秘になりやすい
まわりの人が気づいて声をかけることも大切です
うつ病のサインは、本人すら気づかないこともあります。
身近な人に「いつもと違う」と感じたら、こんな声かけが効果的です。
- 「最近元気がないけど、大丈夫?」
- 「何か困ってることがあったら話してね」
- 「疲れているように見えるけど、無理してない?」
まずは話を聞く姿勢を。無理に聞き出すよりも、「あなたのことを気にかけている」という姿勢が安心感につながります。
専門機関への相談をためらわないでください
「つらい」「消えてしまいたい」と思うほどの状態は、病気が引き起こしている感情です。
自分や大切な人のために、次のようなサポート機関を利用しましょう。
- 社内の産業医や人事担当者
- 外部カウンセラー
- 心療内科・精神科
※必要であれば、同伴してあげることも支えになります。
適切な支援のために気をつけたいこと
決めつけない:「◯◯病だよ」と断定しない
精神論で励まさない:「頑張れ」は逆効果なことも
一人で抱え込まない:自分の限界を知ることも大切
最後に
「その一言、その気づきが、大切な人を支える第一歩になります。」
心の不調は、誰にでも起こり得る「ごく身近なこと」です。
あなたの気づきと声かけが、誰かの人生を救うきっかけになるかもしれません。
「笑顔をどれだけ上書きできるか」
それは、私たちが誰かの苦しみに寄り添い、希望を届けようとするときに、そっと胸に刻みたい言葉です。
たとえ今がつらくても、また笑顔で歩き出せるように……。
そんな未来を、私たちは一緒につくっていきたいと願っています。
